あれは確か小学四年生の時のこと。
当時住んでいた家の近所に古びた空き家があった。長年手入れされておらず、今にも壊れそうな状態。木造でサイズも小さく、家というより「小屋」に近い外観だった。あまり通ることのない裏路地にあったため、普段目にすることはほとんどない。ただ、学校へ行くための近道になっていたので、遅刻しそうな時などはその空き家の前を横切ることがあった。
ある日の放課後、俺は友達のつよしと近所の公園で遊んでいた。当時はサッカーに夢中で、その日も時間を忘れてボールを蹴っていた。
楽しい時間はあっという間に過ぎていく。
辺りが夕焼けに染まる頃、俺は何の気無しに周囲を見渡した。すると、グラウンドの隅の方に何かが見えた。よく見ると、白髪の老婆と男の子が手をつないで立っている。初めて見る顔だ。男の子は俺たちと同じくらいの背格好をしている。祖母が孫を連れて遊びにきたのだろうか。
しばらくしても、老婆と男の子は動くことなくその場にとどまっていた。相変わらず、俺とつよしの方をじっと見ている。俺たちは構わずボールを蹴り続けた。
そのうち空が暗くなってきたので、その日は帰宅することにした。
自転車にまたがって公園を出る。俺は少し気になって公園の方を振り返った。
あの二人はまだ手をつないで公園の隅に立っている。そしてこちらをじっと見つめていた。
次の日もつよしと公園に行った。いつも通りボールを蹴っていると、またしても老婆と男の子が公園の隅にいた。昨日と同様、手をつないでじっとこちらを見ている。いつからいたのだろう。全く気付かなかった。
少しして、俺たちは休憩を取ることにした。
「昨日から、おばあさんと男の子がこっち見てるよな?」
俺はつよしに聞いてみた。
「うん。あの二人、何やってるんだろう」
つよしも気づいていたようで、俺は少し安心した。
「男の子、仲間に入れてほしいのかな?声かけてみる?」
俺がそう聞くと、つよしは「嫌だよ」と冷たく返した。結局、俺たちは二人を無視してサッカーを続けることにした。
次の日もまた、老婆と男の子は公園の隅に現れた。そして変わらずこちらを見ていた。
その次の日は雨がぱらついていた。それでも状況は同じだった。俺とつよしはボールを蹴り合い、老婆と男の子は公園の隅からそれをじっと見ている。
雨の日はボールが滑りやすい。案の定、その日はミスキックが多かった。
「次はちゃんと俺の方に返せよ!」
俺はミスを連発するつよしをからかうように言った。つよしは「わかったよ!」と言って足元のボールを蹴った。だが、やはりまたミスキックになった。ボールは明後日の方向に飛んでいく。そして、何かに導かれるように、老婆と男の子の方に転がっていった。俺は急いでボールを追いかけ、二人の足元に止まったボールを拾いあげた。顔を上げると、ふいに男の子と目が合った。小さな黒目が印象的で、命が宿っていないかのような乾いた瞳だった。俺はとっさに「一緒にやる?」と口にした。どうしてその言葉が出たのかはわからない。自分の意思だったのか、何かの力が働いていたのか、答えは今も謎のままである。男の子は俺と目を合わせたまま、ゆっくりとうなずいた。
それから俺たちは三人でパス回しをした。ただ、男の子はまったく楽しそうではなかった。無表情でただボールを蹴るだけ。こちらが話しかけても、首を縦か横に振るだけの反応だった。俺は正直頭にきた。こちらが誘ってあげたのだから、もう少し楽しそうにやれよ、と思った。だから、10分くらいパス回しをしたところで「今日は帰る」と言って、つよしと一緒に公園を出た。老婆には挨拶もしなかった。
次の日、俺は公園に行くか迷っていた。俺の中で、老婆と男の子が面倒な存在になっていたのだ。正直言って、すごく気味が悪かった。だが、つよしは強気だった。「なんで俺たちが公園を諦めなきゃいけないんだよ」「昨日で満足しただろ。今日は来ないよ」などと説得してくる。結局、俺はつよしの勢いに押され公園に行くことにした。
その日はつよしの予想通り、老婆と男の子は来る気配がなかった。嫌な視線から解放され、俺たちは思う存分ボールを蹴り合った。
だがしばらくすると、つよしの様子が急におかしくなった。ボールを持ったまま固まっている。
「どうした?早く蹴り返せよ!」
俺は大きなな声で叫んだ。
「…」
つよしは固まったままだ。口を半開きにして俺の方を見ている。
その時、背後に何かの気配を感じた。とっさに振り向くと、目の前には、老婆と男の子が立っていた。距離は1メートルもない。二人は手をつないでこちらを見ている。次の瞬間、老婆が口を開いた。
「うちに遊びにおいで」
かすれた声でそう言った。意味が分からなかった。直観的に「相手にしてはダメだ」と思った。俺は急いでつよしの方に走って行き、二人で逃げるように公園を出た。
それからは、公園へは行かなくなり、老婆と男の子に会うこともなくなった。
しかし、数ヶ月が過ぎたある日、俺は予想外の出来事に遭遇する。その日、俺は放課後に用事があったので、授業が終わると急いで学校を飛び出した。
校門を出て、家に向かって全速力で走る。家まであともう少し。時間はギリギリだった。俺はどうしても用事に遅れたくなかったため、近道をすることにした。
冒頭に書いた「古びた空き家のある裏路地」を通ることにしたのだ。
どんよりとした狭い道を走って駆け抜ける。
例の空き家は路地の中程にあった。俺はスピードを上げてそこを横切ろうとした。だがその時、建物の方から変な気配を感じた。
足を止めて空き家の方を見ると、そこにはあの老婆と男の子が立っていた。ボロボロの玄関の前で手をつなぎ、こちらを見ている。
俺は怖くなって、すぐにその場から立ち去った。あそこには誰も住んでいないはず。そもそも今にも壊れそうな状態で、人が住めるような家じゃない。しかも、あの男の子は間違いなく小学生の年齢だ。急いで学校を出た俺よりも早く家にいるのはおかしい。なぜ二人はあんなところにいたのだろうか。
その日の夜、両親や祖父母に空き家のことを聞いたが、皆「あそこには昔から誰も住んでいない」と口を揃えた。結局、帰りの出来事は謎のままだった。
それから俺は、いくら急いでいてもあの家の前を通らないことにした。
その後、引っ越しをしたこともあり、この出来事の記憶は次第に薄らいでいった。
ここからは、つい先日の話になる。
仕事の関係で、昔住んでいた町に行く機会があった。俺は仕事が終わると、周辺を少し歩いてみることにした。この町に来るのは約二十年ぶりだ。歩いているだけですごく懐かしい気持ちになる。
俺はふと、あの空き家のことを思い出した。遠い昔の出来事なので、怖さは消えている。さすがにもう残ってはいないだろうが、見に行ってみよう。俺はそう思い、空き家へと向かった。
狭い裏路地を一歩一歩進む。ここは何も変わっていない。今でも日当たりが悪くジメジメしている。
直後、俺は自分の目を疑った。空き家がまだ残っていたのである。全体が朽ち果てていて、ほとんど全壊と言ってもいいくらいだ。俺は写真を撮ろうと思い、スマホを家に向けた。何枚か撮影していると、画面に異様なものが映り込んだ。それはなんと、あの二人の姿だった。玄関の前に立ってこちらを見ている。スマホから目を離し、肉眼でも確認した。やはりいる。しかも、昔のままの姿で。白髪の老婆と、小学生くらいの男の子。
次の瞬間、男の子が老婆の手を離してこちらに駆け出してきた。小さな黒目で俺を見ている。俺は恐ろしくなり、急いで逃げた。路地を抜けたところで振り返ると、男の子の姿はなかった。
あの老婆と男の子は、いったい誰だったのだろう。なぜ、昔のままの姿で存在したのか。そしてなぜ追ってきたのか。俺に恨みでもあったのか、それとも伝えたいことがあったのか…答えは誰にもわからない。
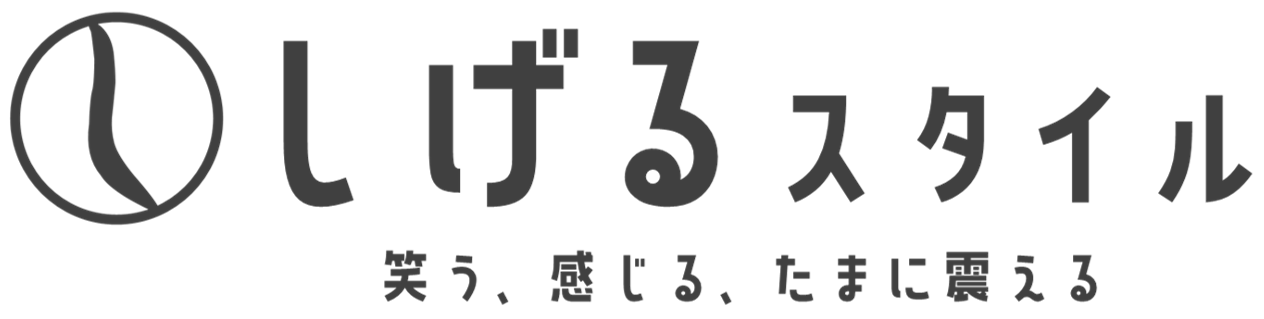



コメント