連れていかれたのは地下にある隠れ家的なバー。落ち着いた雰囲気の音楽が流れている。たぶんジャズだ。カウンターに腰掛けると、支社長はすぐに目の前の初老の男性に「どうも、マスター」と声をかけた。どうやら行きつけの店らしい。奥の棚に並べられたボトルを指さし、ドリンクをオーダーしている。「ツーフィンガー」とかいう聞き慣れない名の酒だった。ふいに「お前は何にする?」と聞かれたので、俺は「じゃあ同じものを」と答えた。「それっぽくなるかな」と思い、右手のツーフィンガー(人差し指と中指)を立てながら言った。

少しキザ過ぎただろうか。マスターは微笑した。しばらくすると、ウイスキーのロックが俺の前に置かれた。初めてお目にかかる丸い氷には驚いたが、反応するとかっこ悪いと思ったので平静を装った。
「じゃあ乾杯」
支社長の言葉とともにグラスを合わせ、ウィスキーを喉に通す。一口飲んだだけで体が熱くなるのを感じた。
「久しぶりに中山の本気を見たよ」
支社長は穏やかな口調でそう言った。俺はその言葉に少し引っかかった。確かに今回、中山課長の「本気」によって業績が回復した。だが、「久しぶり」とはどういう意味だろうか。
「過去にも今回のようなことがあったんですか?」
俺は単刀直入に疑問をぶつけた。
「あいつ、昔は常に本気だった」
俺は、支社長が言っている意味が分からなかった。俺の中で中山課長の印象は、いつも無気力で、可もなく不可もなく、のらりくらりと仕事をするタイプの人間だ。そんな課長が常に本気だったなんて信じられない。
「俺と中山が若い頃同じ支社にいたことは知ってるだろ?」
俺が「はい」と答えると、支社長は静かに言葉を続けた。
「当時、会社の規模はまだまだ小さかった。でもその分『これから大きくしていくぞ』みたいなエネルギーは他のどの競合よりも強かったと思う。社風も今以上に体育会系でな。俺たち若手は馬車馬のように働かされた」
支社長は昔を懐かしむようにそう言った。
「激務に耐えられず辞めていくやつも多くいたよ。でも、俺や中山は死に物狂いで頑張った。そうしてると次第に結果もついてきて、二人揃って表彰されたこともあったな」
俺は心底驚いた。支社長はわかるとして、中山課長にそんな過去があったなんて信じられない。
「今じゃ想像できないだろ?でも本当なんだ」
支社長はそう言って俺の方を見た。まっすぐな視線が俺の瞳に向けられている。どうやら、からかわれているわけではなさそうだ。
「でも、どうして…」
「今はあんなふうになってしまったんですか?」と続けようとしたが、課長に失礼だと思い、飲み込んだ。俺が戸惑いを隠せずにいると、支社長はグラスに残ったウイスキーを勢いよく飲み干し、話を続けてくれた。
「当時俺たち二人は、忙しいながらも仕事にやりがいを感じていた。毎日ヘトヘトで苦しかったけど、それ以上の充実感があった。でも、ある日を境に雲行きが怪しくなってきた」
「何があったんですか?」
俺は酒を飲む手を止めて話に聞き入った。
「人事異動で上司が変わったんだ。そいつが狂ったやつでな。今思い出しても嫌になるよ」
支社長はそう言って、両手で顔を覆った。嫌な過去に蓋でもするかのようだった。話によると新しい上司は悪の権化のような人間で、部下は酷いパワハラを受けたらしい。若かりし頃の支社長と中山課長も例外ではなく、計り知れない程の苦痛を味わったそうだ。「大熊営業部長みたいな感じですか?」と俺が問うと、「くまモンなんて可愛いもんだ」と即答された。営業部長もかなりのパワハラ系だが、それを凌駕するほどの悪質さだったという。
「初めのうちは耐えてたんだが、人間の精神力には限界がある。それで、ある日事件が起きた」
「事件ってなんですか?」
俺はそう言って唾を飲み込んだ。
「その日、俺も中山も徹夜が何日か続いていて、疲れはピークに達していた。徹夜の理由は上司からの指示。人のキャパを考えずに、なんでもやらせてくるやつだった。そんな状況で仕事してたら、上司が突然『今すぐ会議室に入れ』って言ってきたんだ。俺たちは言われるがままに会議室に入った。そしたらいきなり罵声を浴びせられてな」
「どうしてですか?」
俺のグラスの丸い氷は、かなり小さくなっている。でも、酒を飲む気にはなれない。それよりも、早く話の結末が知りたい。
「別に理由はないんだ。チームの業績が悪いことへの怒りを、俺たちにぶつけたかっただけだろう」
なんでこれくらいのことができないんだ
お前はクズか
やる気がないなら今すぐ辞めろ
お前なんて生きてる価値がない
とんでもなく汚い言葉を投げつけられたらしい。
「それで、中山の我慢が限界に達したんだ。完全に吹っ切れたあいつは、上司に強い言葉で反抗した。ちょうど、この前くまモンに反論したみたいに。いや、あれより強い口調だったな」
「それで、どうなったんですか?」
「上司は激怒した。その日以降、中山への当たりがより一層以上に強くなったんだ」
支社長は「あの時、なんで助けてやれなかったんだろう」と言って、自分が何もできなかったことを悔やんだ。でも、それは仕方がないと俺は思う。支社長だって壮絶なパワハラを受け、極限まで追い込まれていたそうだ。そんな時に人を助ける余裕なんてない。
「今思えば、あんなパワハラに耐えようとするなんてどうかしてる。でもあの頃の俺たちは、冷静な判断ができなくなってた。標的にされた中山は特に辛かったと思う。それで、あいつはついに心を壊してしまった。会社に来れなくなったんだ」
課長にそんな過去があったなんて、想像もしなかった。
悲しみや同情や怒り。色んな感情が一緒になって俺を襲う。でも、なんの言葉も出てこない。支社長は何も言わず、新しく運ばれた酒を一口、二口と飲み進めた。俺のグラスの氷はどんどん小さくなっていく。
「それから、課長はどうなったんですか?」
しばらく気持ちを落ち着かせた後、なんとか言葉を振り絞った。
「一年くらい休職してた。復帰した後は、お前の知ってるあいつだよ。以前のような熱意は無くなって、ただ淡々と、できるだけ目立たぬように仕事するようになった」
俺は課長のことを、ただのやる気のない上司としか思っていなかった。元々そういう人間なんだと。でも、そうではなかった。課長は、二度と同じ目に遭わぬよう、自分を殺しているのだ。
部下をそこまで追い込んだ腐った上司は、その後も会社に居座り続け、俺が入社する少し前に引退したそうだ。
支社長は「俺は別に、昔の中山に戻ってほしいとは思ってない」と言った。「あいつが決めればいいことだ。周りが押し付けてもしょうがない」とも。俺もそう思う。
少し沈黙が続いた後、支社長は「でも、心のどこかで期待してるんだ。昔みたいに一緒に本気で仕事したいなって」と漏らし、また勢いよく酒を飲み干した。
「マスター、同じものをもう一杯」
支社長はそう言って空のグラスを持ち上げた。俺はすっかり薄くなってしまったウイスキーを飲み干し「僕も同じものを」と言った。今日はとことん飲みたい気分だ。
翌朝、昨夜のアルコールと重い気持ちを引きずったまま出社した。俺以外のメンバーはいつも通り仕事をしている。思いがけず知ってしまった中山課長の過去。そのせいで、課長を見る目が変わってしまった。ある意味では、見直した部分もある。過去を引きずるそぶりも見せず仕事をこなす姿は尊敬に値する。一方で、心配な面もある。本社との会議以降、課長は大熊営業部長に目を付けられているのだ。毎日のように電話がかかってきて、辛辣なことを言われ続けている。××食品との再契約について報告しても「それくらいできて当然だ」と一蹴されたらしい。このままでは、昔のように心を壊してしまってもおかしくない。課長のためにも、どうにかして営業部長からの信頼を勝ち取らなければならない。それ以降、俺は入社以来最大の熱意で仕事に取り組んだ。
だが、仕事はそんなに甘くない。俺の力などたかが知れている。何の結果も出せないまま、時間だけが過ぎて行った。
そんなある日、またしても予期せぬ出来事が起きた。今度は吉田さんではなく、もう一人の後輩女性社員である長谷川さんが大型の受注を取ってきたのだ。
「嘘だろ?」
松さんは後輩の言うことをがっつり疑っている。長谷川さんは「本当です」と返した。
「そんな金額は絶対無理だ。あり得ない」
それでも松さんは信じない。
「じゃあこれ見てください」
長谷川さんはそう言って松さんに契約書を突きつけた。松さんは「あり得ないあり得ない」と言いながらそれに目を通す。契約金額が記載されている箇所で、松さんの目の動きが止まった。
「ほんまや!!」
明石家さんまさんがよくやっている「ほんまや!」のネタを純粋にやる人を初めて見た。
それにしても、長谷川さんはどうしてこんな大きな成果を掴むことができたのだろうか。実は、この契約にも中山課長が大きく関わっていた。この記事の冒頭に書いた、長谷川さんが提案した新しい営業手法の話を覚えているだろうか?なんと、長谷川さんはその提案を課長の力を借りて実現したらしいのだ。かなり荒削りでリスクのある内容だったため、俺や松さんは到底実行できないと思っていた。でも、中山課長は彼女の熱意を尊重し、最大限のサポートをしてくれたらしい。長谷川さん曰く「私は何もしてません。ほとんど課長の仕事です」とのことだ。
この実績が反映すれば、チームの業績は一気に向上するだろう。全国首位に躍り出る可能性だってある。
「中山、さすがだな!よくやった!」
突然、事務所に大きな声が響き渡った。外出先から戻ってきた支社長だ。事務所に入るなり、真っ先にこちらに向かってきた。課長からの報告を受け、飛んで帰ってきたらしい。
「課員の努力のおかげです」
課長はいつも通り冷静で、かつ謙虚だ。まるで自分は何もしていないかのような態度を取っている。実際は相当な努力をしたはずなのに。きっと今回の一連の行動は、純粋に部下のためにしたことなのだろう。自分の評価を高めたいとか、上司に認められたいとか、課長からそんな思いは一切感じられない。
その時、突然課長の携帯が鳴った。どうやら営業部長からの着信のようだ。俺は「せっかく良い雰囲気だったのに邪魔しやがって」と心の中で悪態をついた。課長は慌てて通話ボタンを押し、電話に出る。
「もしもし、中山です」
また高圧的なことを言われるのだろうか。想像しただけでも憂鬱だ。
「そうですね。ありがとうございます。」
課長の返事は予想外に明るかった。表情からは微かに笑みがこぼれている。その後も、珍しくハリのある声で「ありがとうございます」と繰り返す課長。どうやら、今回の大型案件の話が営業部長にも伝わったようだ。課長の受け答えから推察して、褒められているに違いない。ついに営業部長に認められたのだ。
でも、なぜこんなに早く営業部長の耳に届いたのだろう。課長や長谷川さんが直接報告するとは思えない。となると、伝えたのは一人しかいない。そう思って、ふいに支社長の顔を見ると、無言で右手の親指を立て、俺の方にウインクを飛ばしてきた。俺は気色の悪さを感じるとともに、とても嬉しい気持ちになった。
「課員の努力のおかげです」
課長は営業部長にも同じことを言っている。「少しくらい自分をアピールすればいいのに」と俺は思う。
ほどなくして通話が終了すると、課長は「フー」と大きく息を吐き、満足気な表情で支社長の方を見た。
「お祝いだ!」
支社長の大きな声が事務所いっぱいに響いた。
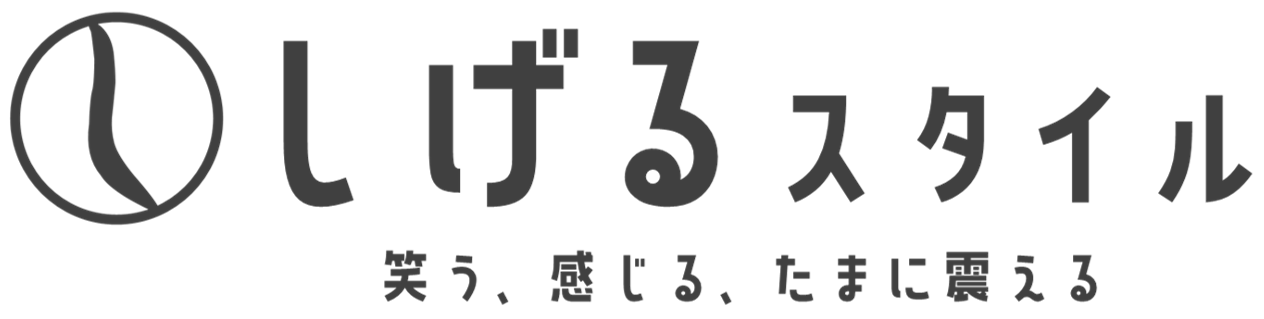

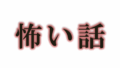
コメント