先日、同じチームの松永係長と同行した。「先輩社員の営業を見て学ぶことも重要」と会社から命令されてのことだ。
松永係長は55歳。うちの会社では、大抵の社員は40代後半くらいで課長に昇格する。55歳で係長ということは…お察しの通りである。正直、学べるものは少なそうだが、俺はまだ平社員だし仕方がない。
俺の在籍するチームは5人体制で、リーダーの中山課長、松永係長、俺、それに後輩2人のメンバー構成である。中山課長はマネジメント専任で担当顧客は持っていないため、必然的に俺の同行相手は松永係長になる。
同行の指示を受けたあと、課長から個別に呼び出され「頼むな」と肩を叩かれた。その言葉には「あまり学ぶものはないと思うけど、会社からの指示だから上手くやってくれ。本社への報告もいい感じに頼むな」という意味が込められていた。俺は「わかりました」と答えた。俺も課長も、上からの指示には誠実に従う人間なのだ。一方、松永係長は全く逆のタイプ。言いたいことは遠慮せず言い、我が道を突き進む人間だ。だから社内外に敵を作りやすい。他にも、発言が適当だったり、デリカシーが無かったり、毎日必ず定時で退社したり、ウエストポーチをつけていたりと、見習うところがほとんどない人である。
でも、俺は不思議と松永係長のことを嫌いになれない。振り切っている感じがうらやましかったりする。見た目は強面だが、ぽっちゃりしていてマスコット的なかわいさがある。
松永係長、通称「松さん」との同行日、俺が出社すると松さんが何か叫んでいた。
「ない!ない!俺のコンピュータがない!」
どうやら自分のパソコンが見当たらないようだ。パソコンをコンピュータと呼ぶところが松さんらしい。
「昨日、壊れたって言ってシステム室に預けてたじゃないですか」
女性社員が冷静に伝えると、松さんはホッとした様子で額の汗を手のひらでぬぐい、その手をジャケットで拭いた。おれはシンプルに「汚いな」と思った。
その後無事にコンピュータを取り戻した松さんだったが、すぐに次の壁にぶつかった。
「ヤフーが開かない!」
俺が「ヤフー以外のページは見れるのか」と聞くと「ヤフーがダメなのに他のページが見れるわけないだろう」という回答が返ってきた。なるほど。松さんは全てのWEBページはヤフーを入口にしていると考えているようだ。
確認したところ機内モードに設定されていたので、解除方法を教えてあげた。松さんは「やっぱりそうか」と言っていたが絶対に理解していない。そしていつも通り、人差し指だけでキーボードを打ち始めた。
出発の時間になり、松さんと2人で会社を出る。今日はあいにくの天気だ。傘をさして駐車場へ向かった。営業車に乗り込むと、運転席の松さんはカバンから何かを取り出し、顔に近づけた。
サングラスだ!雨の日に営業車でサングラスをかける人なんて初めて見た。小ぶりで真円のサングラスをかけた松さんは、大きめの鼻とベージュの上着も相まって、俺に「紅の豚」を想起させた。

松さんは次に、運転席と助手席の間にある収納ボックスを空けた。そこには10枚ほどのCDが並んでいた。「今時、営業車にCD並べてる人いるのかよ…」と心の声が漏れそうだったが、なんとかこらえた。Bluetoothの存在を教えてあげようかとも思ったが、面倒くさくなりそうなのでやめておいた。
「しげるはどんなアーチストが好きなんだ?」
アーティストをアーチストと呼ぶところが気になったが、スルーして「米津とかですかね」と答えた。すると松さんは「俺、音楽には詳しいよ」みたいな顔をして「米津けんじか。悪くないな」と返してきた。“けんじ”ではなく“けんし”である。
「米津けんし、いいですよね」
俺はあえて“し”の部分を強調して言った。
「そうだな、米津けんしには才能を感じる」
松さんは、間違いなど初めから無かったかのようにナチュラルに訂正した。
「YOASOBIとかも良く聞きます」
俺はよく聞くアーティストとして別の例を出した。
「あの曲もいいよな。米津っぽさが出てる」
どうやら松さんは米津の曲名と勘違いしたようだ。完全に知ったかぶりを決め込んでいる。
次に「何か聞きたい曲あるか?」と問われたので、お気に入りの邦楽を何曲か答えた。松さんは「よし、わかった」と言ってCDを選び、プレイヤーに吸い込ませた。
流れてきたのはなぜかビートルズだった。俺は「なんでだよ!」と心の中で突っ込んだ。さっきの質問はなんだったのだろうか…
俺の戸惑いを置き去りにし、松さんは車を発進させた。
出発して30分程度。松さんの運転は至って普通だ。ただ一点だけ気になる点があった。急ブレーキの度に、左手を俺の胸の前に伸ばしてくれるのだ。好きな男子にやられたら女子は「キュン」とすると聞いたことがある。しかし30代のおっさんが50代のおっさんにやられても、誰も得をしない。
そうこうしていると、最初の商談先に到着した。従業員50人ほどの決して大きいとは言えない町工場。自動車や電化製品に使われる金属部品を製造しているらしい。一方、うちの会社は求人サイトを運営している。俺たちのミッションは、この町工場の求人情報を自社サイトに掲載してもらい、掲載料を頂くことである。
受付で名を告げると、社長室に通された。これくらいの規模の会社だと、社長と直接面談することも少なくない。5分ほど待っていると、60代後半くらいの貫禄のある男性が入ってきた。ギョロリとした目で俺たち2人を交互に見ている。緊張しつつも名刺交換をして商談を開始した。
松さんが提案内容をプレゼンする。俺は同行させてもらっている立場なのでほとんど口を出さなかった。ひと通り話が終わったところで、社長から鋭い質問が飛んできた。
「で、応募は集まるのか?」
顧客にとってはここが最も重要なポイントだ。
いくらお金をかけて求人を出しても、応募が集まらなければ意味がない。
「御社であればかなり応募が来ると思います!!」
松さんは自信満々に発言した。俺は不安になった。給与などの条件が弱いため、明らかに応募が集まりにくい案件だったからである。
実はこれが松さんのいつもの手口なのだ。とにかく応募が集まると言い切る。自信満々に言えば結構相手は信じてくれるもので「じゃあ任せてみよう」となる。ただ、松さんの場合はなんの根拠もなく言ってしまうのでタチが悪い。その上、契約してもその後のフォローが甘いので、当然結果は出ない。そのため、新規顧客と契約件数はそれなりに多いものの、クレームや短期間での解約がとても多いのである。チームメンバーは松さんのことを密かに「ご新規クラッシャーの松」と呼んでいる。
だがこの手法は誰にでも通用するわけではない。この日商談した社長は厳しい口調でこう言った。
「その根拠はなんだ?」
短い言葉だったが、とても迫力があった。松さんはまた、額の汗を手のひらでぬぐってジャケットで拭いた。俺は冷静に「汚いな」と思う。松さんは早口でこう答えた。
「正直ベースで申し上げまして、応募は来ると思います、はい。御社と同じような条件で結果が出た事例がありますのでね。直感ベースでは、目標の応募数は超えられると思いますよ、はい。お願いベースではありますけども、掲載していただけませんか?松永ベースでは自信があります」
「ベース」が多い。意味もよくわからない。特に最後の「松永ベース」ってなんだよ。
「話にならん」
社長の一言で商談は終了した。
次に俺たちが訪れたのはIT企業。と言っても従業員30人くらいの小さな会社だ。ネット通販系のビジネスをしているらしい。駅前の小綺麗なビルに本社があった。出迎えてくれたのは20代後半と思われるかわいらしい女性。目がクリッとしていて小動物みたいだ。俺たちは早速挨拶を交わした。松さんが渡した名刺は指先の汗で湿っている。
ミーティングスペースに通されると、松さんは早速話を始めた。
「御社のことはヤフーベースで調べてきましたが、売上ベースでは好調のようですね?」
「あ、はい」
「やはり人手不足なんですか?現場ベースでは」
「あ、はい」
「ざっくりベースで何人くらい必要なんですか?」
・・・
ざっと数えただけで8回も出てきた。彼の中で「『ベース』という単語を5回以上使え」みたいな縛りでもあるのだろうか。
松さんはその後もこの「ベース話法」を多用してプレゼンを進め、最後にこう締めくくった
「松永ベースでは自信があります」
出た!必殺の「松永ベース」!そしてなんの根拠もない自信!終盤になると、もはや松さんのベース話法を待っている自分がいた。
そして奇跡が起きた。その場で契約が成立してしまったのである。恐るべきベース話法…
「松さんの自信はどこから来るんですか?俺はあんなにはっきり『自信があります』なんて言えません」
商談後の車の中で俺は松さんに聞いた。
「俺たちが信じなくて誰が信じるんだよ」
確かに正論だ。でもそれを言っていいのは契約後のフォローもしっかりやる人だけだと思う。
少しして、松さんはある公園の駐車場に車を停めた。生い茂る木々の隙間から差し込む日差しが気持ちいい。
「少し寝るか」
松さんはそう言って運転席のシートを倒した。ここに駐車した時点で、なんとなくそんな気がしていた。断る理由もないので俺は受け入れた。そしてゆっくりと目を閉じた。
「あ゛ーあ゛ーあ゛ー」
しばらくして、獣のような喘ぎ声で目が覚めた。運転席に目をやると、松さんがのどに手を当てて苦しんでいる。
「大丈夫ですか!?」
俺は焦って声をかけた。
「ああ、大丈夫。落ち着いた」
松さんはなんとか正気を取り戻した。そして言葉を続けた。
「俺、睡眠時無呼吸症候群なんだよ。だから本当は専用の機械付けて寝ないといけないんだけど…昼寝のときは無理だからな」
なんだよその命がけの昼寝は…俺はもうひと眠りしようとした松さんを必死で止めて、次の目的地に向かうように懇願した。
その後も色々ありつつ、松さんとの同行は進んでいった。時刻が午後4時を回ったころ、松さんが言った。
「今から娘迎えに行くから」
「え?」
「今ちょうど娘の高校の近くにいるから、迎えに行くことにした」
「営業中ですよ?課長に許可取りました?」
「まあ大丈夫だろ」
ということで、松さんの一人娘を迎えに行くことになった。どんな娘なのか少し興味がある。松さんに似て破天荒な性格なのだろうか。
学校の近くに車を停車させ、娘さんを待つ。しばらくすると、少し前から一人の女性が歩いてきた。肩まで伸ばした黒髪にセーラー服姿は、どこにでもいる女子高生。だが一点だけ、普通と違う部分があった。右手に白い杖を持っている。そしてそれを地面に当て、左右に振りながら歩いてくる。松さんは車から出て女性の元へと駆け寄った。俺は助手席に座ったまま、その光景を茫然と眺めていた。後部座席のドアが開き、女性が乗り込んでくる。少しして松さんも運転席に座った。
「娘の愛子だ」
松さんは俺にそう告げた。
「お父さん?誰か乗ってるの?」
「言ってなかったな。会社の後輩だ」
俺は言葉を発せずにいた。
「父がお世話になってます」
女性が元気な声で俺に言った。
「いえ、こちらこそ。お父さんにはお世話になってます」
俺はなんとか動揺を隠して答えた。一瞬の沈黙の後、松さんが「行くぞ」と言って車を出した。
娘の愛子ちゃんは生まれつきの全盲だった。つまり、暗闇の中で生きている。でも、そんなことを感じさせないくらい明るい女性だった。本当に松さんの娘なのか疑いたくなるくらい爽やかな女性だ。車内では愛子ちゃんを中心に他愛のない会話が続く。学校のことや普段の松さんのことなど、たくさんの話をした。
「あ、そろそろ充電ヤバいかも!スマホ充電してくれない?」
しばらくして、愛子ちゃんがそう言った。松さんはシガーソケットから伸びた充電コードの先端をつかみ、愛子ちゃんのスマホに刺した。
その瞬間、画面が明るくなり、1枚の画像が映し出された。
海辺で撮った家族写真
写っているのは松さんと愛子ちゃん、もう一人の女性はおそらく奥さんだろう。3人が満面の笑みで体を寄せ合っている。
しばらくして、画面はまた暗闇で覆われた。
俺は車窓を流れる街並みを見ながらふと考えた。
「松さん、会社では適当な人間だけど、愛子ちゃんにとっては良い父親なのかも」
愛子ちゃんを家に送り届け、また松さんと2人きりになった。車内は一転して静まり返った。
「行くとこなくなったし、帰社するか」
「そうですね」
会社に戻る道中、ポケットに入れていた携帯が鳴った。着信画面を確認すると、得意先の部長の名が表示されている。普段はほとんど電話をかけてこない相手だ。俺は少し嫌な予感がした。恐る恐る通話ボタンを押すと、案の定、電話口の向こうから怒鳴り声が聞こえてきた。
「お前、何考えてるんだ?」
「何かありましたか?」
俺は事情が掴めず聞き返した。話を聞くと、うちの求人サイトから全く応募が来ないというクレームだった。俺の対応についても不満に思っているらしい。自分としては精一杯のことをしているつもりだった。徹夜で対応したことも1度や2度ではない。でも、俺の頑張りは相手に伝わっていなかったらしい。
営業センスがあるやつは、結果が出ないリスクに備えて普段から自分の必死さを上手く顧客に伝えている。大抵の場合、かなり大袈裟に。俺はそれが苦手だ。
「今回までで契約は解除する。お前のところには一生頼まない」
最悪の展開だ。必死で説得を試みたが、何も聞いてもらえなかった。一方的に電話を切られた後、俺はしばらく放心状態になっていた。
「大丈夫か?」
運転席の松さんが心配して声をかけてくれた。感傷的になっていた俺は、ついマイナスの発言をしてしまった。
「俺、営業向いてないんですかね?たまにこういうことがあるんです。精一杯やってるつもりなんですけど、上手くいかないんです。成績は同期や後輩に負けてばかりだし」
「向いてなくてもいいんだよ」
「え?」
「人にはそれぞれ個性があるんだ。仕事で活かせる個性のやつもいれば、そうじゃないやつもいる。お前の個性がたまたま仕事に合ってないってだけだろ?だからって他人より劣ってるわけじゃない」
「そうですかね…?」
「出世してるやつは仕事と個性がたまたま噛み合っただけだ。だからって人間として偉いわけじゃない。場所や時代が変われば評価の基準なんて一瞬で変わるんだ。だから他人からの評価なんて気にするな。お前はお前のままで良いんだよ」
悔しいけど、松さんの言葉に救われた。自分を貫いて生きている松さんの言葉だから、余計に説得力がある。
その時、カーステレオから流れていた曲が終わり、次の曲のイントロが流れ出した。シンプルだが心を包んでくれるようなピアノの音色。そして、優しい歌声が車内に響いた。
Let it be, let it be, let it be, let it be…
ビートルズのレットイットビー。松さんの言葉と曲がシンクロし、ポジティブな気持ちが心を満たした。思いがけず、涙が溢れそうになる。気づかれないよう即座に拭い、横目で運転席に目をやった。松さんは何食わぬ顔で運転を続けている。
「カッコイイとは、こういうことさ」
不意に、紅の豚のキャッチコピーが頭に浮かんだ。
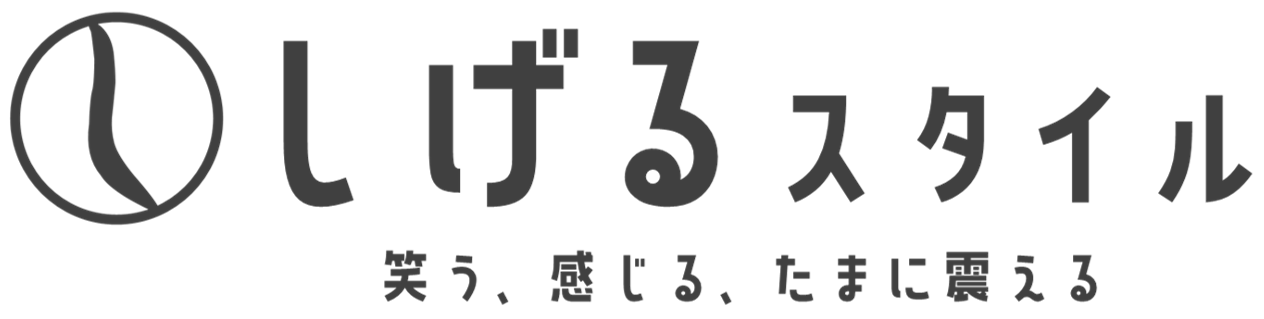


コメント