今日は仕事も休みで暇だったので、のりおを遊びに誘うことにした。電話をかけると、のりおは1コール目で応答した。案の定、暇を持て余しているらしい。俺が「なんかしようぜ」と誘うと、のりおは「いいよ」と即答した。そこまではよかったのだが、二人ともやりたいことがあるわけでもなく、何をするかがなかなか決まらない。そのため、とりあえずノープランで俺の部屋に集合することにした。
チャイムが鳴りドアを開けると、大きな紙袋を手に下げたのりおが立っていた。
「それなに?」
俺が尋ねると、のりおは「スーファミ」と答えた。ご存じ、スーファミとはスーパーファミコンの略称だ。説明不要だと思うが、90年代に大流行した家庭用ゲーム機である。思いもよらない手土産に俺が戸惑っていると、のりおは「二人でやりたいと思ってさ」と付け加えた。スーファミなんて小学生の時以来だ。紙袋から見え隠れするグレーの本体がすごく懐かしい。
「久しぶりにレトロゲームに興じるのも悪くないな」
俺はそう答えて、のりおを部屋に招き入れた。早速テレビに接続して電源を入れる。長い間使っていなかったようだが、問題なく起動した。まず初めに、ストリートファイター2をプレイした。言わずと知れた人気格闘ゲームだ。互いにキャラクターを選び、闘いの幕が上がった。
のりおは異常にゲームが上手かった。逆に俺は下手くそだ。俺の選んだダルシム(手足が伸びるキャラ)はボッコボコにされた。何度挑んでも全く歯が立たない。どうでもいい情報だが、のりおはチュンリー(紅一点の女性キャラ)の使い手だった。鼻息荒くチュンリーを使いこなすのりおを見て若干引いてしまった。
次にドンキーコング2をプレイした。こちらも当時大人気だったので、ご存じの方が多いだろう。一応説明しておくと、横スクロールでステージをクリアしていく仕様になっている。俺たちは、二人で協力して進んでいくモードを選びプレイした。やはり、のりおは異常に上手かった。俺の出る幕はほとんどない。彼はディクシーコングというヒロインキャラの使い手だった。チュンリーといいディクシーコングといい、フィメールキャラへの謎のこだわりはなんなのだろうか。
俺たちは時間を忘れてゲームに没頭した。気付けば外は夕焼けに染まっている。昼ご飯も食べていない。さすがにやり過ぎだと思い、休憩することにした。ストックしていた賞味期限が切れる寸前のインスタントラーメンを作り、二人で食べる。冷蔵庫に冷やしていた缶ビールも空けた。
早い時間から飲むビールは最高だ。そんなに飲むつもりはなかったが、2本、3本と空き缶が増えていった。のりおも俺と同じペースで飲んでいる。
「仕事は順調?」
のりおが唐突に聞いてきた。
俺は「まあまあかな」と答えた。のりおは「いいなあ。俺は全然ダメ」と返した。
話を聞いてみると、仕事でなかなか成果が出ないことに悩んでいた。
「俺、なんの取り柄もないからな」
のりおはそう言ってため息をついた。「そんなことないって」と否定したが、のりおの暗い表情は変わらない。なんとか元気付けたいが、どうしたらいいだろう。
「じゃあ、お互い好きなところとか強みを言い合おうぜ!」
俺は酔いに任せてそう言った。ただの思いつきだが、お互いに相手の長所を言い合えば、少しは気持ちが晴れるだろうと思ったのだ。
のりおは初め「なんでそんなことするんだよ」と乗り気ではなかったが、必死の説得により、最後はやることに合意した。俺はなぜあそこまで必死になったのだろう。たぶん、のりおのためというよりも、俺の方が好きなところを言って欲しかったのだ。
「目標は100個な!」
今思い出しても恥ずかしいくらいに、俺は張り切っていた。
「じゃあ1個目発表するぞ。せーので一緒に出すんだからな!」
話し合った結果、一個ずつ付箋に書いて発表する形式をとった。
「せーの!」
俺の掛け声で互いの付箋を見せ合う。のりおは『頑張り屋』と書いていた。
「なるほどね」
俺はとりあえずそう言った。本当はとても嬉しかったが、それを前面に出すのはカッコ悪いと思って、感情を抑えた。これまで人から「頑張り屋」なんて言われたことはない。でも、自分では密かに「俺って意外と頑張り屋」と思っている。だから、のりおが初めて評価してくれて嬉しかった。
一方、俺が付箋に書いた言葉は『やさしい』だった。これまでのりおが怒ったところをほとんど見たことがないし、今日だって俺を楽しませようとゲームを持ってきてくれた。周りに気遣いができる、優しい男だと思う。のりおは「そんなことないだろ」と謙遜しつつも、少し嬉しそうだった。
「じゃあ二個目行くぞ!せーの!」
次にのりおが書いたのは『誠実さ』だった。これは意外である。これまで、自分のことを誠実だと思ったことはあまりない。「これが二個目に出てくるってことは、俺って人の目には結構誠実に映っているのか…」そう思うと、じわじわと喜びが湧いてきた。思いがけず自分の良さを知り、少し浮かれ気分になったが、それでも喜びは表に出さないよう努めた。手で顎を触りながら、あくまでクールに「なるほど」と返しておいた。

一方、俺が書いたのは『集中力がある』だ。のりおは何かに熱中すると、異常なまでの集中力を見せる。その点は俺の父によく似ている。
例えばこの前、漫画の「NARUTO」にハマり、丸一日かけて全72巻と外伝1巻を読破してしまった。読んでいる間は寝食を忘れていたらしい。その後の数週間、語尾が「だってばよ」になっていたことが印象深い。今でも興奮するとそうなることがある。
また、「ゴルゴ13」にのめり込んでいたこともある。その時は約200巻を三日で読破していた。読み終えた後の目つきはデューク東郷のように鋭かった。その後の数週間、背後に立たれることをやたらと警戒していたことが印象深い。
以上はあまり良い例ではないが、彼の集中力は使い方によってすごい武器になると思う。俺の付箋を見たのりおは「そうかなあ」とまた謙遜した。本当は嬉しいに違いない。
その後も、俺たちはいくつか好きなところを出し合った。当たり前の話だが、だんだんと書くことがなくなってくる。そうなると、思いつくのは極めて具体的で細かい内容になっていった。
例えば、「割り勘の計算が早い」とか「膝がきれい」とか「声の大きさがちょうどいい」とか「目がいい」とか…
しばらく続けていたが、どうにも浮かばなくなってきたので、次で最後にすることにした。数えてはいないが、おそらく20個くらいは出し合ったのではないだろうか。目標の100個には遠く及ばないが、頑張った方だろう。
俺は最後に何を書こうか悩んだ。もう何も出てこない気がしたが、諦めずに必死で考えた。日頃ののりおについて思い返す。彼にはどんないいところがあるか。何か得意なことはないか。そして、なんとか一つ思いつくことができた。一方、のりおの方も悩んだ末に付箋に何かを書き記していた。
「じゃあ最後いくぞ!せーの!それ!」
俺たちは勢いよく付箋を見せ合った。
「なんでやねん!」
のりおの付箋を見た瞬間、俺は思わずそうツッコんだ。関西人でもないのに関西弁で。なぜツッコんだかというと、二人の付箋に同じ言葉が書いてあったからだ。
『ゲームが上手い』
そんなはずはない。ついさっきまで一緒にゲームをしていたのだから、のりおは俺の実力を知っているはずだ。ストリートファイター2ではほとんどのりおの勝利だったし、ドンキーコングでは俺の出る幕がなかった。
「お前なに適当なこと書いてんだよ!」
俺は少し感情的になって言った。
「は?どこが適当なんだ?」
のりおは俺の言ってる意味が分かっていない様子だった。
「俺がゲーム下手だって知ってるよな?」
「うん」
「それならお前が『ゲームが上手い』って書くのはおかしいじゃないか!」
「どういうこと?」
なぜ伝わらないんだろうか。仕方ないので細かく説明してやった。
「いいか?ゲームが上手いのは、のりおの強みだろ?だから俺が『ゲームが上手い』って書くのは正しいよな?そして俺はゲームが下手なんだ!お前は俺の強みを書かないといけないんだから『ゲームが上手い』って書くのはおかしいだろ?」
「え?そういうルールだったの?俺は俺のいいところを書くんだと思ってた」
俺は耳を疑った。まさかの展開だ。なんと、のりおは初めから自分自身の好きなところや強みを書いていたらしい。「二人とものりおのいいところを書く」というルールだと勘違いしていたのだ。
「なんでやねん!」
俺はまた関西弁で突っ込んでしまった。
「だって、俺を励ますためにやってくれたんだろ?」
「それはそうだけどさ!俺もいいところ言われたいじゃん!」
密かに喜んでいた俺の気持ちはどうなるんだ…こんなことなら、もっと派手に喜んでおけばよかった。「なるほど」などとカッコつけて済まさずに。そうすればのりおも勘違いに気づいたはずだ。
「そうか…悪かったな」
のりおは素直に謝ってくれた。だが、俺の気持ちは収まらない。どうしていいかわからず、ソファーに身を預け、仰向けになった。
少しして、のりおが俺の手に何かを握らせた。見ると、それは付箋だった。
『友達思い』
その紙切れには、そう書かれていた。
「お前のいいとこだ」
のりおはボソッとつぶやいた。そして「今日は帰るわ」と言って立ち上がった。俺は「待てよ」と引き留めて言葉を続けた。
「もう少しゲームしようぜ」
のりおは一呼吸置き、笑顔で次のように答えた。
「もちろんだってばよ!」
そして俺たちはまたゲームに夢中になった。次に選んだのはマリオカート。
のりおがチョイスしたキャラは、もちろんピーチ姫だった。
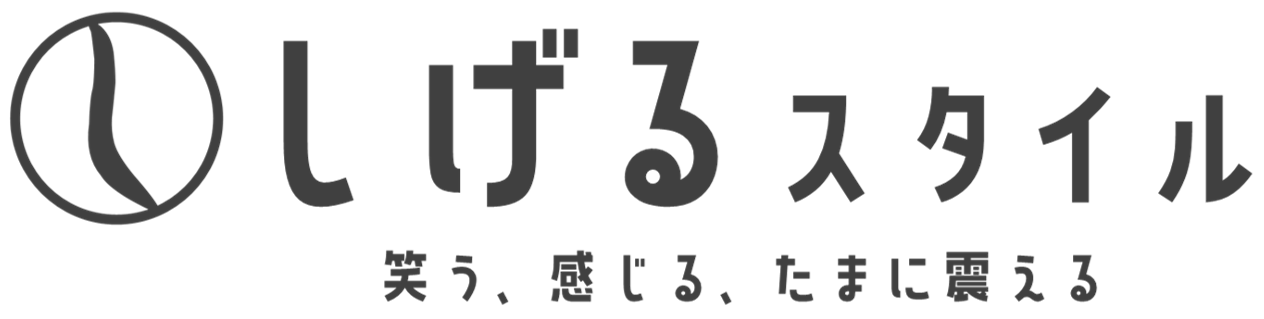
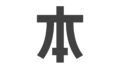
コメント